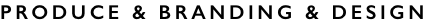町工場に化学反応を起こすPBブランド開発

美術木箱うらたは、美術品向け桐箱の製造を手掛けています。桐の収納箱の歴史は長く、古くは長持(ながもち)として貴重品や衣服の保管に用いられ、江戸時代後期から近年にかけては桐箪笥として、嫁入り道具の代表的なものとされていました。現在でも、陶磁器や掛け軸、漆器など、工芸品の収納箱として桐が用いられています。
近年、伝統工芸品の生産量は大きく減少しており、桐箱のニーズも下降の一途をたどっています。あたらしい需要の開拓の必要性を感じ、私たちに相談がありました。
自社工場をもち、そして職人がいる環境を活かせる新しい事業として自社商品の企画・販売を行うことになり、何をどのように考えていくかというスタート地点において、まずは原点に戻るべく桐という素材がもつ機能性を改めて深堀りしていきました。
高級工芸品の保管に桐が用いられてきたのは、木肌や木目の清楚な美しさはもとより、その高い機能性に理由があります。桐には調湿機能や、防虫機能のほか、抗菌や防腐効果もあるとされています。日本は一年を通じて湿気が高く、四季の豊かな移り替わりは、季節ごとの大きな寒暖差をもたらします。こうした特有の気候条件の中、大切なものを良質なコンディションで保管するのに適した素材が桐だったのです。
桐の持つ調湿性能が最も生かされるシーンとして、キッチンを想定しました。美術桐箱の「大切なものを守る」という伝統的な位置づけは変えなくとも、現代の私たちにとっての大切なものには「家族の健康」や「幸せな日常」も入るのではないかと考えたときに、食品を良い状態で保管できるキッチンストッカーという商品へと結びついたからです。キャッチフレーズに「食の美味しいは、美しい保存から生まれる」という言葉を用い、美術品用桐箱を作ってきた「うらた」の誇りを感じさせるものとしました。
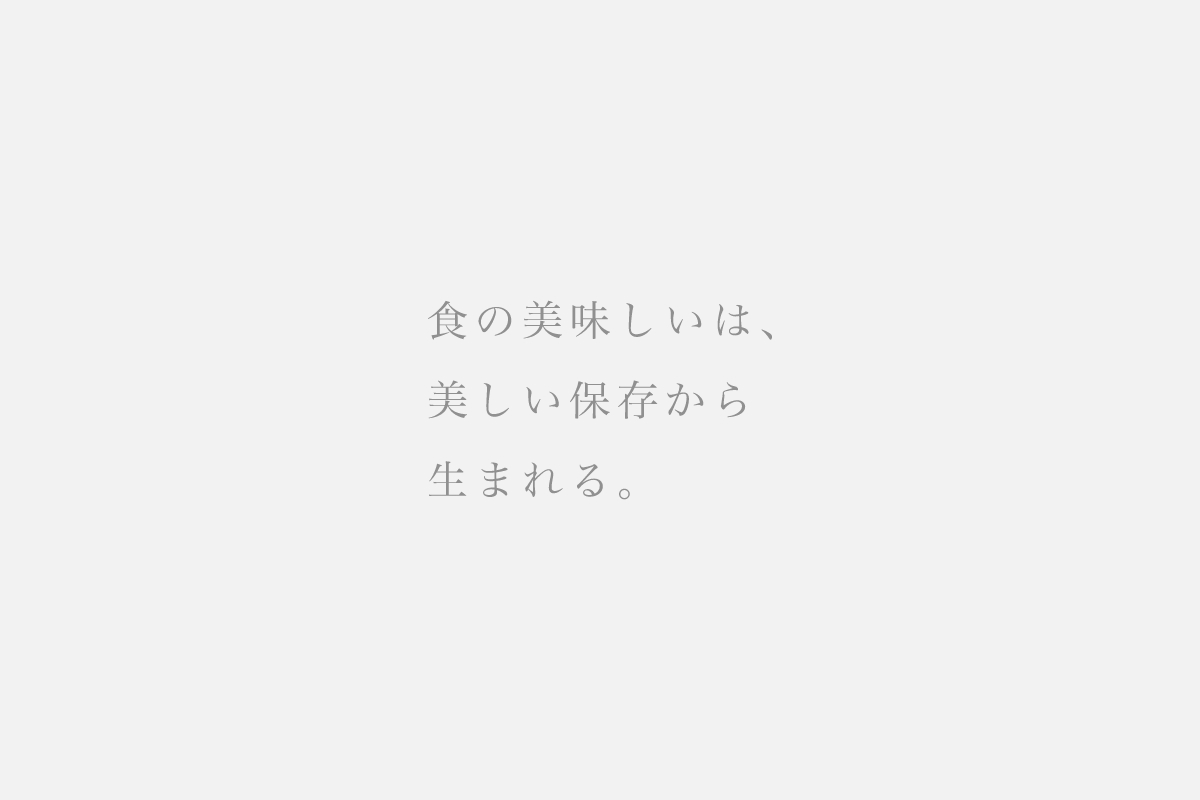
コンセプトが決まれば、商品づくりに入っていかなければなりません。一般の家庭のキッチンに、桐箱が置いてあるケースは稀です。そのため「食品の保存に桐箱どうですか」といっても、すぐに理解されるのは難しいと考えました。また、市場には様々な機能をもつ競合製品が溢れている状態でもあります。私たちは、まずは“商品をデザインする”ということをやめました。
キッチン空間には住み暮らす人のこだわりが詰まった空間です。商品だけを見てデザインされた商品は、空間に置かれた際にかならず生活にノイズを生み出してしまいます。重要なことはキッチンに冷蔵庫や炊飯器があるように、違和感なく桐箱が置いてあるシーンを表現し、自然に受け入れられることです。そう考えたときに、もっとも参考になるのはキッチン家電でした。
スマートフォンなどに代表されるように、先端のデジタル機器はデザインがよりシンプルになっています。余計なスイッチやボタンが必要でなくなったことに加え、時代の感性に対応した結果ともいえるでしょう。特に最近は、洗練されたデザインのキッチン家電が増えています。私たちは手作りのクラフトですが、あえて最先端のデジタル家電のようなミニマムでモダンなデザインを志向しました。
3Dモデリングによるデザインと検証を何度も行い、現代のキッチンにも違和感なく溶け込めるデザインを追求しました。また、持ちやすく、使いやすいことも重要なポイントでした。

この時、カギとなったのは職人の技術です。「美術木箱うらた」の職人は、きわめて洗練された技術を持っています。高い密封性が求められる美術木箱を作るには、驚くほど緻密な加工技術が必要なのです。
日本の工業製品は、限りない均一性を追求し、きわめて低い不良率で世界の信頼を得てきました。このストッカーは、職人技でありながら、工業品にも引けを取らない精緻さ・正確さを保っています。各辺のナチュラルなカーブや取手の代わりに着けたアールのある細い切り込みも、すべて職人の手わざによって生まれています。手元の技術だけで寸分の違いもなく加工する技によって、このストッカーは最先端家電の並ぶ現代のキッチンにも違和感なく溶け込む作品となりました。
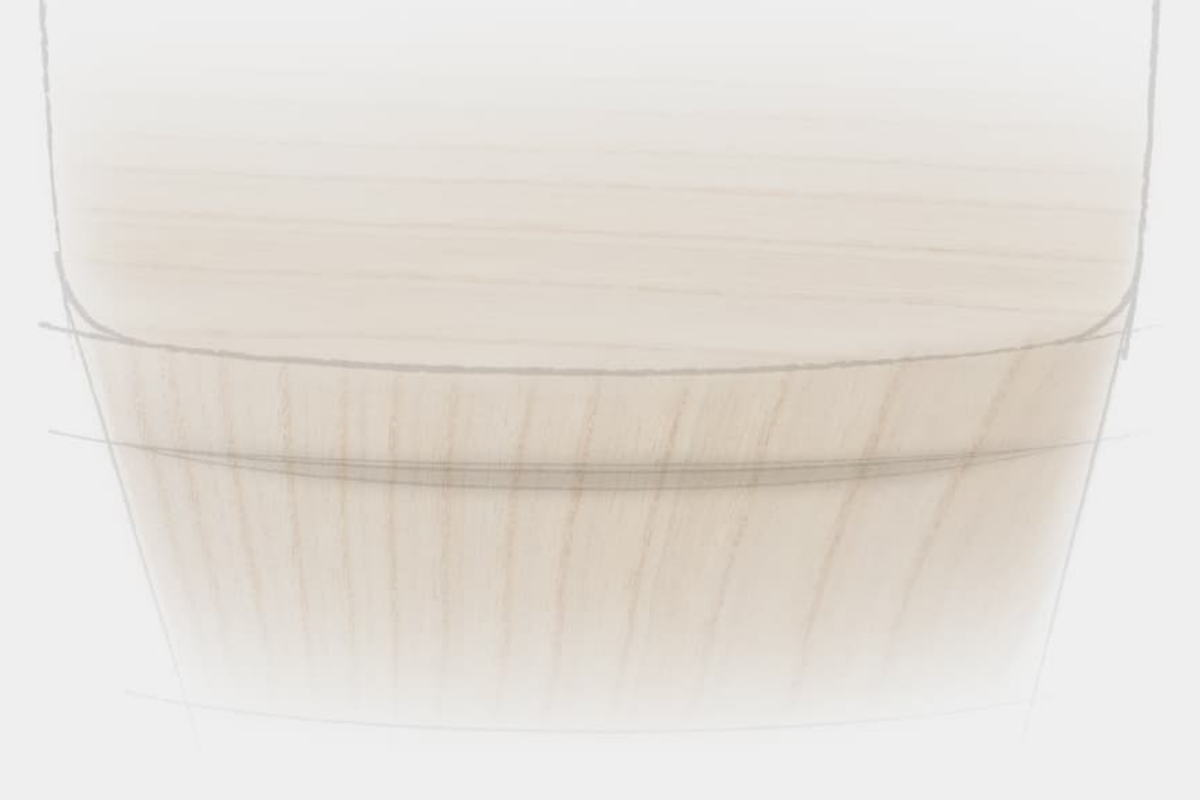
KIRIFTの製品は、地元である富山県において「とやまブランド」及び「TOYAMA PRODUCTS」にも選定され、また「おもてなしセレクション2021」にて金賞を受賞、また林野庁が主催する「ウッドデザイン賞」を受賞するなど、各界から高い評価をいただいています。
本業の強みを活かしたPBを武器としてもち、各種展示会にでることで新たな出会いが創出されます。ブランドだけではなく事業母体である美術木箱うらたの認知も広まり、KIRIFTのストーリに共感してくれるなど、興味を持った他業種からオーダーの桐箱の依頼が舞い込んでくるなど、本業へも良い循環が生まれてきます。
また、定期的に新商品の開発を行うなど可能性の模索をとめることなく活動しています。発表前の新商品を展示会にもっていき様々なバイヤーから得られるフィードバックをもとに洗練させていくなど、多くの人に求められるブランドになるべく両社一体となって取り組み続けています。
自社の強みを活かした商品開発という枠におさまらず、経営自体に良い化学反応を起こすことをデザインの力で証明した事例となりました。